| 明治維新 1868年(明治元年) 歴史年表 真日本史 (人名事典)(用語事典) |
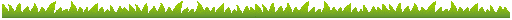

 主要メンバーは、岩倉具視、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文というまさに明治維新の主役たちであった。
主要メンバーは、岩倉具視、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文というまさに明治維新の主役たちであった。
| 明治維新年表 | |||
| 1867年 | (慶応3年) | 10月14日 | 大政奉還 |
| 1867年 | (慶応3年) | 12月9日 | 王政復古の大号令 |
| 1868年 | (慶応4年) | 1月3日 | 戊辰戦争開始 |
| 1868年 | (慶応4年) | 3月14日 | 五箇条の御誓文布告 |
| 1868年 | (慶応4年) | 4月11日 | 江戸城無血開城 |
| 1868年 | (慶応4年) | 7月17日 | 江戸を東京に改称 |
| 1868年 | (明治元年) | 9月8日 | 元号を明治に改元 |
| 1868年 | (明治元年) | 9月22日 | 会津藩降伏 |
| 1868年 | (明治元年) | 10月13日 | 江戸城を皇居とする |
| 1869年 | (明治2年) | 5月18日 | 戊辰戦争終結 |
| 1869年 | (明治2年) | 6月1日 | 版籍奉還 |
| 1871年 | (明治4年) | 5月10日 | 新貨条例 |
| 1871年 | (明治4年) | 7月14日 | 廃藩置県 |
| 1871年 | (明治4年) | 11月10日 | 岩倉使節団出発 |
| 1873年 | (明治6年) | 1月10日 | 徴兵令 |
| 1873年 | (明治6年) | 7月28日 | 地租改正条例 |
| 1873年 | (明治6年) | 9月13日 | 岩倉使節団帰国 |
| 1873年 | (明治6年) | 10月23日 | 征韓論争が起こる |
| 1874年 | (明治7年) | 2月1日 | 佐賀の乱(士族の反乱) |
| 1876年 | (明治9年) | 3月28日 | 廃刀令 |
| 1876年 | (明治9年) | 8月5日 | 秩禄処分→士族の乱が相次ぐ |
| 1877年 | (明治10年) | 2月14日 | 西南戦争 |
| 1881年 | (明治14年) | 10月12日 | 国会開設の勅諭 |
| 1885年 | (明治18年) | 12月22日 | 内閣制度ができる |
| 1889年 | (明治22年) | 2月11日 | 大日本帝国憲法発布 |
大政奉還
1867年(慶応3年)10月14日、江戸幕府の第15代将軍徳川慶喜が政権を
朝廷に返上することを申し入れ、翌15日、朝廷はそれを受け入れた。
これによって鎌倉幕府以来、約700年続いてきた武家政治は終了した。
王政復古
1867年(慶応3年)12月9日、天皇は王政復古の大号令を発した。
これは、徳川慶喜の将軍辞職と、徳川家の領地没収を意味するものであった。
これにより、天皇が総裁・議定・参与の三職を通じて行政権を行使する
明治政府が発足(1867年12月9日)した。
戊辰戦争
1868年(慶応4年)1月3日から1869年(明治2年)5月18日まで行われた新政府軍と
旧幕府側との戦いの総称。
鳥羽・伏見の戦い、上野戦争(彰義隊の戦)、会津戦争、箱館戦争などを含む。
五か条の御誓文
1868年(慶応4年)新政府が天皇中心の体制を固めるために、天皇が神に誓う形で、
五か条の御誓文を公布した。ひろく意見を聞いて政治を行い、外国から新しい知識を
取り入れて国を発展させていこうというもの。
元号を明治に改元
1868年(慶応4年/明治元年)9月8日、明治改元の詔が発せられ、慶応4年を明治元年とした。
あわせて、天皇一代に元号を一つとする「一世一元」の制が定められた。
版籍奉還
版籍奉還は、領地と領民を天皇へ返上し、幕藩体制の解体と中央集権をはかった政策である。
「版」とは領地、「籍」とはそこに住む人々を指す。
幕府が倒れた後も、国内は諸大名がそれぞれ統治を続けていたため、新政府は大名に
版籍を国に返すように働きかけたのである。
大名は、その後も藩知事(地方長官)として藩政を委任され、その身分と収入が
保たれたため、特に大きな混乱もなく、諸大名の領地・領民が天皇に返還された。
新政府は、版籍奉還と同時に、公家・大名諸侯の呼称を廃止して華族制度を導入し、
公家142家、大名諸侯285家が華族として認められた。
新貨条例
1871年(明治4年)新しい貨幣制度確立のために公布された法令。
江戸時代の複雑な貨幣制度を整理して貨幣単位を円、補助単位を銭・厘とし、金本位制採用をうたった。
廃藩置県
廃藩置県は、すべての藩を廃止して、府県に統一し、中央集権体制の強化をはかった政策。
旧藩知事はすべて東京移住を命じられ、代って府知事・県令(のちの県知事)が
中央から派遣。
全国は、3府72県の行政単位に統一、天皇を中心とする中央集権国家の統治基盤が確立した。
岩倉使節団
1871年(明治4年)政府は、不平等条約の改正を外交の方針とし、その下交渉と欧米の事情を
調べることを目的として、岩倉具視らを欧米使節団として派遣した。
征韓論
明治初期の朝鮮征討論。明治維新以来、政府は朝鮮にしばしば国交を求めたが、朝鮮は排外鎖国政策をとっており
これを拒否したため、1873年(明治6年)西郷隆盛、板垣退助、江藤新平らは、士族の不満を外戦に向けるため
「征韓」を強く唱えて政府の方針を決定した。
しかし欧米視察から帰国した岩倉具視、大久保利通らは内治を優先せよとしてこれに反対、西郷らは敗れて
下野した(明治六年の政変)。士族反乱、自由民権運動の原因となる。
佐賀の乱
1874年(明治7年)2月、佐賀の不平士族が江藤新平を指導者として蜂起した事件で、
士族反乱の最初のもの。政府軍に敗れ江藤らは処刑された。
廃刀令
軍人・警察官にのみ帯刀を認め、士族などの帯刀を禁止した法令。1876年(明治9年)公布。
秩禄処分
1876年(明治9年)明治政府が金禄公債証書の交付を代償として、華族・士族への家禄支給を全廃した処置。
これにより多くの士族は急速に没落した。
西南戦争
1877年(明治10年)鹿児島の士族が西郷隆盛を担いで政府に反乱を起こした。
反乱軍は、近代的な政府軍に敗れ、西郷は自害。
武力による反抗はこれが最後となり、不平士族の反政府運動は言論が中心となった。
大日本帝国憲法
伊藤博文らが渡欧して研究し、君主権の強いプロイセン憲法を手本にして草案をつくり、
1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法が発布された。
主権は天皇にあり、国務大臣や官吏は天皇が任命し、議会は政府を組織する権限をもたない。
外国と条約をむすんだり、戦争を始めることもすべて天皇の権限であった。
特に軍部は天皇に直属するものとして、政府からも議会からも独立していた。
また、国民は「臣民」とよばれ、その権利は法律によって制限できるとされていた。