| 国名 | ナイジェリア連邦共和国 |  |
 |
||
| 英語 | Federal Republic of Nigeria | ||||
| 首都 | アブジャ(Abuja) | ||||
| 独立年 | 1960年10月(イギリス) | ||||
| 主要言語 | 英語、ハウサ語 | ||||
| 面積 | 92万3768km2 | ||||
| 人口 | 1億9063万2261人(2017年推計) | ||||
| 通貨単位 | ナイラ | ||||
| 宗教 | イスラム教51%、キリスト教48% | ||||
| 主要産業 | 原油、液化天然ガス |
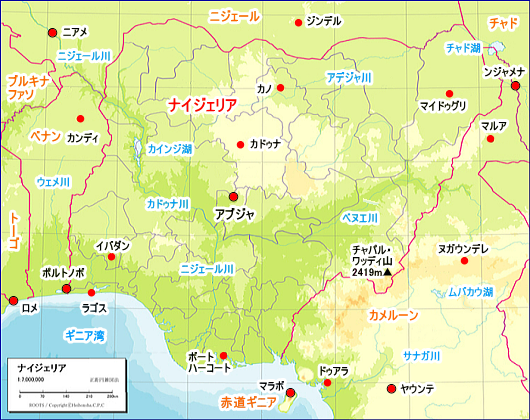
![]()
地理
南部は高温多湿の熱帯雨林気候。
5〜10月の雨季には特に雨量が多く、マングローブが生い茂り熱帯風土病も多い。
北上するにつれて乾燥し雨季が短くなる。北部はサバナ気候、国境付近は乾燥気候。
1950年代、ニジェール川デルタ一帯に石油が発見され、輸出の約 9割を原油を中心とした
鉱物燃料が占める。ほかにカカオ、ゴムなどを輸出。
地下資源はほかに石炭、スズ、コロンブ石などを産し、鉄、鉛などを大量に埋蔵している。
工業は石油精製のほかは織物、セメント、食品加工など軽工業が主。
古来、部族の移動が激しく、人種、言語とも 200をこえるが、
おもなグループは北部のハウサ族、西部のヨルバ族、南東部のイボ族で、
北部はハウサ族を中心にイスラム教徒が大部分。
全体ではイスラム教徒とキリスト教徒がほぼ半数ずつ。
公用語は英語。ハウサ語、ヨルバ語、イボ語なども広く用いられる。
首都アブジャは、標高 360mの台地に位置する。
国会、行政府、外国大使館などが位置する中心地区と、近代的な宿泊施設、商業ビルなどが立ち並ぶ周辺地区からなる。
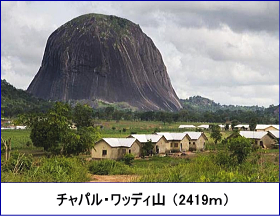 高速道路で主要都市と結ばれ、空港もある。面積 7315km2。人口 140万5201(2006年推計)
高速道路で主要都市と結ばれ、空港もある。面積 7315km2。人口 140万5201(2006年推計)
歴史
15世紀末ポルトガル人による奴隷貿易の拠点となり、沿岸部は、かつて奴隷海岸と呼ばれた。
1914年、イギリスの植民地となり、1960年、イギリス連邦内の自治国として独立。
1967年、南東部のイボ族が反イギリスを掲げ、ビアフラ共和国として独立を宣言。
世に「ビアフラの悲劇」と呼ばれる内戦状態に入り、200万人に及ぶ餓死者を出した。
1970年、ビアフラ側の降伏で内戦終結をみたものの、相次ぐクーデターで政情不安は
とどまらず現在に至る。
| 1914年 | イギリスの植民地に |
| 1960年10月 | イギリス連邦内の自治国として独立 |
| 1963年10月 | 共和制に移行し、ナイジェリア連邦共和国が成立 |
| 1966年 | 軍事クーデターで軍政に移行 |
| 1967年 | ビアフラ戦争勃発(〜1970年) |
| 1979年 | 民政に移管、第二共和政(〜1983年) |
| 1983年 | 再び軍部が政権を握る |
ビアフラ戦争 (Biafran War)
多民族国家ナイジェリアは、北部のハウサ族、西部のヨルバ族、
 そして南東部のイボ族の三大民族を有している。
そして南東部のイボ族の三大民族を有している。
1967年、南東部のイボ族が「ビアフラ共和国」の独立を宣言するが、
政府はこれを認めず、内戦に突入した。
部族対立と宗教対立から戦火は拡大。
さらにビアフラ側にフランスと南アフリカが、政府軍側にはイギリスと
ソ連が援助したため、内戦は国際紛争の性格を帯びた。
1970年1月、ビアフラ軍の無条件降伏で内戦は終結したが、
200万人もの餓死者とそれを上回る数の難民を生んだ。