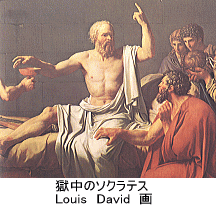
死は、刻一刻と近づいてくる。
しかし、ソクラテスは、まったく死を怖れなかった。
意に介さなかった。なぜなら、彼は心の底から魂の不死を確信していたからである。
彼は魂の不滅について、連日、獄舎にやってくる多くの弟子たち、青年たちに、くりかえし、霊魂の不死を説きつづけた。
だが、彼を取り囲んで、その話に耳を傾ける者たちのほとんどは、魂が永遠に生きる、などということを、
論理的には理解しても、実際には信じられなかった。
それゆえ、ソクラテスが魂の不死を力説すればするほど、その主張は、みずからの死を覚悟し、取り乱さないために、
自分自身に言いきかせているのではないかと、ひそかにそう思っていた。
それにしても、あと数日の猶予しかない牢獄での毎日を、足に鎖をつながれながら、かくも平然と死についてのみならず、
徳について、正義について、国家について、法について、善・悪について、倦きることなく淡々と語りつづけ、
若者の疑問に懇切に答えているソクラテスという人物のふるまいに対して、みな一様におどろき、畏敬の念を禁じ得ないのだった。
実際、ソクラテスは、その生涯において、しばしば神の声をきいている。
その神の声は、彼に、何々をせよ、と命じるのではなく、何々をひかえたほうがよい、と制止する形で彼の行為を指示したのである。
ソクラテスが無実の罪で訴えられ、五百人の陪審員の前で、挑発とも受けとられるような「弁明」を、信じるがままに、堂々と展開したのも、
そして、その結果、当然予想された死刑の判決に、従容として服したのも、神の声が、彼のそうした行為を、何ひとつ制止しなかったからであった。
ソクラテスは裁判の判決に従ったのではなく、自分の信念に反対しない「内在の神」に殉じたのである。
(プラトン 「ソクラテスの弁明」)
Canon in D (Pachelbel)