| 平清盛 1167年 (仁安2年) 歴史年表 真日本史 (人名事典)(用語事典) |
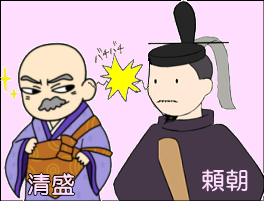
平治元年(1159年)平治の乱が勃発し、平清盛は宿敵・源義朝を破った。
義朝の息子である頼朝は、13歳の若年とはいえ、戦闘に参加しており、斬首の運命が待っていた。
ところが、清盛の継母である池禅尼(いけのぜんに)が頼朝の助命を清盛に嘆願した。
軍記物「平治物語」によると、頼朝が夭折した池禅尼の息子に生き写しだったからだという。
こうして、頼朝は減刑され、伊豆の小島への流刑で済むことになった。
しかし、この決断が平氏の寿命を縮めることになった。
仁安2年(1167年)清盛は、武士として初めて太政大臣に任命されるという快挙を成し遂げた。
治承4年(1180年)2月、清盛の娘・徳子の息子が安徳天皇として即位し、これを機に、
清盛は天皇の外戚となり、その権力は不動のものとなった。
だが同年4月、源頼朝が反平家の兵を挙げ、清盛は衝撃を受ける。
さらに治承4年(1180年)10月、富士川合戦で平家軍が反乱軍に惨敗し、情勢は一変する。
反乱軍の鎮圧に専心し、ようやく平家軍は盛り返すが、翌年2月、清盛は突如熱病に倒れた。
病状は急速に進行し、1181年(治承5年)2月4日、清盛は京の九条河原で死去、享年64。
死期を悟った清盛最期の言葉は「きっと、わが墓前に、頼朝が首を供えよ」であった。
![]()
![]()
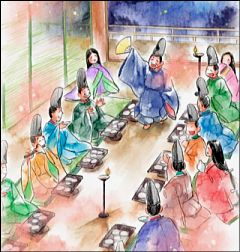
平家物語
平家の栄華と没落を描いた軍記物語「平家物語」は、作者不詳だが、鎌倉時代に成立したと思われる。
「祇園精舎の鐘の声」の有名な書き出しをはじめ、平易で流麗な名文として広く知られる。全十二巻。
巻一「祇園精舎」の段で諸行無常、盛者必衰の理を説いた後、平忠盛の昇殿を契機として
その嫡男・清盛の代に平家が頂点を極めるようになるところから始まる。
以後、繁栄を極める平家と反感を抱く後白河法皇とその近臣たちとの対立、そして後白河法皇の幽閉、
後白河法皇の皇子・以仁王(もちひとおう)の平家追討の号令と落命と続くが、頼朝挙兵の報の後、
清盛の死により平家の命運は大きく傾いていく。
信濃で挙兵した木曾義仲が平家の大軍を撃破し、平家に代わって京を制圧する。
しかし頼朝は、義仲が先に京に入ったことを快く思わず、鎌倉から義仲追討の指示を出す。
頼朝から派遣された義経は義仲を討伐し、次いで都落ちした平家を追って、軍を西に進め、
一ノ谷合戦、屋島合戦に勝利する。敗走する平家は長門国・壇ノ浦へと逃げ落ちる。
これら源平の合戦が物語の縦糸とするならば、横糸として事件や人物の余話および和漢の故事、たとえば
源頼政の鵺(ぬえ)退治、勅撰歌人・忠度や琵琶の名手・経正の都落ちのさまなどが挟まれる。
巻十一は、母・二位尼と愛息・安徳天皇の入水を見て、後を追う建礼門院徳子が源氏に捕らわれ、
宗盛・重衡などの平家の武将が次々と処刑されるところで巻を終える。
----------------------------------------------------------------------------------
| 平安時代(794年〜1192年) | ||||||
| 794年 | (延暦13年) | 平安京遷都 | ||||
| 802年 | (延暦21年) | 坂上田村麻呂 蝦夷を降伏させる | ||||
| 866年 | (貞観8年) | 藤原良房が摂政となる | ||||
| 887年 | (仁和3年) | 藤原基経が関白となる。 | ||||
| 894年 | (寛平6年) | 菅原道真が遣唐使の廃止を提唱 | ||||
| 1016年 | (長和5年) | 藤原道長が摂政となる | ||||
| 1051年 | (永承6年) | 前九年の役(〜1062) | ||||
| 1083年 | (永保3年) | 後三年の役(〜1087) | ||||
| 1086年 | (応徳3年) | 白河上皇が院政を開始 | ||||
| 1095年 | (嘉保2年) | 北面の武士を置く。武士の台頭 | ||||
| 1156年 | (保元1年) | 保元の乱 | ||||
| 1158年 | (保元3年) | 後白河天皇、上皇に | ||||
| 1159年 | (平治1年) | 平治の乱 | ||||
| 1160年 | (永暦1年) | 源頼朝、伊豆に流罪 | ||||
| 1167年 | (仁安2年) | 平清盛が太政大臣となる。平氏全盛期 | ||||
| 1169年 | (嘉応1年) | 後白河上皇、法皇に | ||||
| 1179年 | (治承3年) | 平清盛、後白河法皇を幽閉 | ||||
| 1180年 | (治承4年) | 安徳天皇即位 | ||||
| 1180年 | (治承4年) | 以仁王、源頼朝挙兵 | ||||
| 1180年 | (治承4年) | 富士川の合戦 | ||||
| 1181年 | (養和1年) | 平清盛死去 | ||||
| 1183年 | (寿永2年) | 後鳥羽天皇即位 | ||||
| 1184年 | (寿永3年) | 一ノ谷の戦い | ||||
| 1185年 | (元暦2年) | 壇ノ浦の戦いで平氏が滅亡 | ||||
| 1185年 | (元暦2年) | 源頼朝、守護、地頭の任命権を得る | ||||
| 1185年 | (元暦2年) | 源義経、奥州へ落ちる | ||||
| 1187年 | (文治3年) | 藤原秀衡、義経を匿う | ||||
| 1189年 | (文治5年) | 源義経、自害 | ||||
| 鎌倉時代(1192年〜1333年) | ||||||
| 1192年 | (建久3年) | 源頼朝、征夷大将軍となる(鎌倉幕府) | ||||
| 1221年 | (承久3年) | 承久の乱 幕府軍が朝廷軍を破る | ||||
| 1232年 | (貞永1年) | 御成敗式目を制定する | ||||
| 1274年 | (文永11年) | 元・高麗軍が対馬・壱岐を襲撃し、 | ||||
| 九州に上陸する(文永の役) | ||||||
| 1281年 | (弘安4年) | 元・高麗軍、再度襲来(弘安の役) | ||||
| 1297年 | (永仁5年) | 武士の窮乏を救うため、徳政令を発令 | ||||
| 1331年 | (元弘1年) | 元弘の変 | ||||
| 1333年 | (元弘3年) | 足利尊氏、新田義貞挙兵、 | ||||
| 鎌倉幕府(北条氏)滅亡 | ||||||
| 1334年 | (建武1年) | 後醍醐天皇による建武の新政 | ||||
| 1336年 | (建武3年) | 湊川の戦い | ||||
| 1336年 | (建武3年) | 足利尊氏が北朝の天皇を立て | ||||
| 南北朝時代始まる | ||||||
平家の盛衰と鎌倉幕府
保元の乱で後白河天皇方についた平清盛と源義朝は、それぞれ武士団を率いる棟梁であった。
やがて二人は対立、平治の乱(1159年)で敗れた義朝は殺され、息子の頼朝は伊豆に流された。
ほどなく平清盛は太政大臣になった。平家一門は高い官職を独占し「平家一門にあらざれば、
人ではない」とさえ豪語する輩も出てきた。だが平家の権勢を快く思わない者も出てきた。
後白河天皇は出家して法皇となっていた。
武士を利用して大きな権力を築いた後白河法皇だが、協調関係だった平清盛が政治の
実権を握るようになると、不満を持ち始め、一転して平氏打倒を図るようになった。
やがて法皇の側近の貴族たちが、平家打倒を計画する。
清盛はそれを見つけて処罰し、後白河法皇も幽閉、清盛の孫である幼い安徳天皇を位につける。
1180年(治承4年)後白河法皇の皇子・以仁王(もちひとおう)が平家打倒の兵を挙げた。
伊豆に流されていた頼朝が呼応して挙兵すると、代々源氏に仕えていた武士たちが続々と
馳せ参じた。
平清盛は頼朝追討の軍勢を派遣し、源平両軍は富士川をはさんで対峙した。だが源氏方の盛んな
勢いを見た平家軍は、戦わずして敗走。頼朝は、弟の義経に平家追討を命じた。
1185年(元暦2年)義経は讃岐国・屋島に平家を急襲し、さらに長門国・壇ノ浦に追い詰めた。
義経との壇ノ浦の戦いに敗れた平家は、安徳天皇とともに海中に没し、ここに平家一門は滅亡した。
頼朝の勢力増大を恐れた後白河法皇は、軍事に優れた源義経を重く用い、頼朝追討の命令を下した。
だが頼朝を重んじる武士たちは動こうとせず、孤立した義経は、奥州藤原秀衡のもとに落ち延びる。
1189年(文治5年)秀衡の死後、その子の藤原泰衡は義経を殺害し頼朝との協調をはかった。
しかし頼朝は自ら大軍を率いて奥州に進み、藤原一族を滅ぼした。
1192年(建久3年)法皇の死去にともない、源頼朝は、後鳥羽天皇より征夷大将軍に任ぜられた。
頼朝は、源氏ゆかりの地、鎌倉を根拠地として政権を樹立、ここに鎌倉幕府が成立した。