
 Top Page 中国語講座
Top Page 中国語講座
【第五課 第五節】 小説読解
「我是猫」 夏目漱石
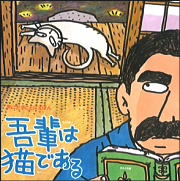 咱家是猫。名字嘛 …… 还没有。
咱家是猫。名字嘛 …… 还没有。
哪里出生? 压根儿就搞不清!
只恍惚记得好像在一个阴湿的地方咪咪叫。
在那儿,咱家第一次看见了人。
而且后来听说,他是一名寄人篱下的穷学生,属于人类中最残暴的一伙。
相传这名学生常常逮住咱们炖肉吃。
不过当时,咱家还不懂事。倒也没觉得怎么可怕。
只是被他嗖的一下子高高举起,总觉得有点六神无主。
咱家在学生的手心稍微稳住神儿,瞧了一眼学生的脸,
这大约便是咱家平生第一次和所谓的 “人” 打个照面了。
当时觉得这家伙可真是个怪物,其印象至今也还记忆犹新。
单说那张脸,本应用毫毛来妆点,却油光崭亮,活像个茶壶。
其后咱碰上的猫不算少,但是,像他这么不周正的脸,一次也未曾见过。
况且,脸心儿鼓得太高,还不时地从一对黑窟窿里咕嘟嘟地喷出烟来。
太呛得慌,可真折服了。
如今总算明白: 原来这是人在吸烟哩。
咱家在这名学生的掌心暂且舒适地趴着。
可是,不大工夫,咱竟以异常的快速旋转起来,
弄不清是学生在动,还是咱家自己在动,反正迷糊得要命,直恶心。
心想: 这下子可完蛋喽!又咕咚一声,咱家被摔得两眼直冒金花。
只记得这些。至于后事如何,怎么也想不起来了。
蓦地定睛一看,学生不在,众多的猫哥们儿也一个不见,
连咱的命根子——妈妈也不知去向。
并且,这儿和咱过去呆过的地方不同,贼拉拉地亮,几乎不敢睁眼睛。
哎哟哟,一切都那么稀奇古怪。
咱家试着慢慢往外爬,浑身疼得厉害,原来咱被一下子从稻草堆上摔到竹林里了。
好不容易爬出竹林,一瞧,对面有个大池塘。
咱家蹲在池畔,思量着如何是好,却想不出个好主意。
忽然想起: “若是再哭一鼻子,那名学生会不会再来迎接?”
于是,咱家咪咪地叫几声试试看,却没有一个人来。
转眼间,寒风呼呼地掠过池面,眼看日落西山。
肚子饿极了,哭都哭不出声来。
没办法,只要能吃,什么都行,咱家决心到有食物的地方走走。
----------------------------------------------------
【注 釈】
【我是猫】 wǒ shì māo 「吾輩は猫である」 (わがはいはねこである)
夏目漱石作。1905年 (明治38年)、雑誌 「ホトトギス」 に発表。
英語教師苦沙弥 (くしゃみ) 先生の飼猫を主人公として擬人体で書かれ、
諷刺的な滑稽の中に文明批評を織り込む。
【夏目漱石】 xià mù shù shí 「夏目漱石」 (なつめそうせき) (1867~1916)
小説家。名は金之助。江戸牛込生れ。東大英文科卒。五高教授。
1900年 (明治33年) イギリスに留学、帰国後東大講師、のち朝日新聞社に入社。
1905年 「吾輩は猫である」、次いで 「倫敦塔」 を出して文壇の地歩を確保。
主な著作は 「坊つちやん」 「草枕」 「虞美人草」 「三四郎」 「こゝろ」 「明暗」など。
夏目漱石(1867-1916)日本作家。原名夏目金之助,号漱石。
少年时代爱读中国史书,他的名字即取自「晋书」中「漱石枕流」一语,并有汉诗文集「木屑录」(1889)。
1905年开始发表他的名著「我是猫」。1906年完成中篇小说「哥儿」以及「草枕」和「二百十日」,在文坛上轰动一时。
1907年他宁愿辞去大学教授的职位到报社工作,他认为报社是商业,大学也是开买卖。
最后一部长篇小说「明暗」(1916)没有完成即病逝,这部小说被誉为日本近代心理小说的典范。
他的小说主要是揭露和批判明治维新后的文明社会,思想深刻,笔触锋利。
他主张 「自我本位」,反对当时流行的自然主义,著有「文学论」。有「夏目漱石全集」(十六卷,1960)。
【寄人篱下】 jì rén líxià
他人の厄介になる。居候になる。
【贼拉拉】 zéi lā lā (=极、非常)
やけに。やたらに。
----------------------------------------------------------
【口語訳】
「吾輩は猫である」
私は猫である。 名前だって? …… まだ名前は無い。
どこで生まれたかって? 初めからよくわからん!
何かじめじめした場所で、ひたすらにゃあにゃあ叫んでいたような気がする。
私はそこで初めて人というものを見た。
あとから聞いたことだが、奴は人の家に居候しておる貧しい書生で、
人の中でも、とびきり悪らつな部類に属する生き物だそうだ。
なんでもこの書生というのは、ときどき我々をつかまえて煮て食うらしい。
そのころの私は、なにしろ世間知らずだったもので、別にそれほど恐ろしいとも思わんかった。
そりゃあ奴にひょいと持ち上げられたときには、いささか仰天はしたが。
手のひらの上で少し気を落ち着かせて奴の顔を眺めてやった。
これがまあ、私のいわゆる 「人」 との初顔合わせであろう。
奴は確かに得体のしれない怪物だと感じ入ったものだ。その時の印象が、今なお記憶に生々しい。
だいいちその顔が、本来うぶ毛でしつらえているべきものが、つるつるしておって、まるでやかんだ。
その後、私が出会った猫は少なくないが、奴のあんな不細工な顔には、とんと出くわしたことがない。
のみならず、顔のまん中があまりに突起している。
そうしてその二本の穴から、ときどきぶうぶうと煙りを噴き出しておる。
どうもむせっぽくてじつによわった。
今になってわかったことだが、これは人がたばこを吸っている場面らしい。
この書生の手のひらで、私はひとまず心地良く伏せておった。
しかし、まもなく、恐ろしい勢いでそこが高速回転し始めた。
書生が動くのか、自分が動いているのか、よくわからんかったが、
むやみに目が回って、吐き気をもよおした。
自分はいよいよおだぶつかと思っていると、どさりと倒れこんで、目から火が噴き出した。
そこまでは記憶しているが、あとは一体どうなったのやら、どうしても思い出せない。
ふと目を凝らして見ると、書生はいない。たくさんおった猫の兄弟たちも一匹も見えぬ。
かんじんの母猫も ―― 行方知れずの状況だった。
しかも、今まで過ごした場所とは違い、やけに明るく、目を開けていられぬくらいだ。
はてさて、あたり一面、どうも様子がおかしい。
のそのそと這い出してみると、体中がとんでもなく痛む。、
稲わらの上から、いきなり竹林の中に捨てられてしまったようである。
ようやく竹林を出て、見ると、むこうに大きな池がある。
私は池のほとりにしゃがんで、どうしたらよいか考えた。どうにも良いアイデアが思い浮かばない。
もういちど鳴いてみたら、あの書生がまた迎えに来てくれるかも、と考えついた。
そこで、私は試しににゃあにゃあとやってみたが誰も来ない。
またたく間に、寒風がぴゅうと池の面を過ぎて、日はまもなく西の山に沈もうとしていた。
腹がぺこぺこで、これ以上鳴きたくても声が出ない。
仕方がない、食えさえすればどこでもいい。
私は食い物のあるところまで歩いてみようと決心した。
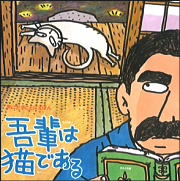 咱家是猫。名字嘛 …… 还没有。
咱家是猫。名字嘛 …… 还没有。