1)「フォーク」とは
フォークソングは、本来「アメリカの各地方の歌」である。

アメリカは言うまでもなく、移民の国である。
それだけでなく、かつてはイングランドやフランスに分割して領有されていた。
故国を離れてアメリカで暮らす移民は、自分の国を懐かしみ、有り合わせの楽器で祖国の音楽を奏でた。
パーティで、家庭で、祭りで、労働の現場でこうした音楽は演奏された。もちろん歌を伴うものが多かった。
しかしアメリカでは他国出身者との交流も不可避であり、故国そのままの演奏が保存されるということはあまりなく、やがて他国の楽器を演奏したり、
あるいは他国のリズムを取り入れたり、と言った形で地方ごとに独特の音楽スタイルが出来てくる。
代表的なものはアパラチア山脈に住んだアイルランド、イングランド、スコットランド人が演奏したカウボーイソング「マウンテンミュージック」である。
この音楽はやがてギターにフィドル(バイオリン)やハワイアンスチールギターを伴う「ウエスタン」や、ギターにベース、
バンジョー(Banjo イタリア移民が持ち込んだマンドリンが起源)を伴い、ハイトーンのボーカルを特徴とする「ブルーグラス」、
ヨーロッパ中部高原地帯由来のヨーデルをフィーチュアした「ウエスタンヨーデル」などに分化していく。
また旧仏領のルイジアナで発生した「ケイジャン」はアコーディオンがメインになる。
このほか「カントリー」の起源となった「ヒルビリー」(アメリカ南部民謡)なども含め、大陸をルーツとしながらもすっかりアメリカオリジナルに変身した音楽が誕生した。
フォークソングとはこのような流れの中で歌い継がれてきた歌達のことである。
1950年代になると、アメリカでは「モダンフォーク」が主として学生の間でブームになる。

中心になったのはピート・シーガー(Pete Seeger)とウッディ・ガスリー(Woody Guthrie)である。
この二人は戦前から各地のフォークソングを収集し、また自作を歌ってきていた。特にピートは40年代始めに戦争に反対し、各地の労働組合で歌っていた。
「民衆の価値観」を歌うその姿勢は政府の反発を買い、1952年「赤狩り」に会うが、それをきっかけに一人で各地の大学を演奏して廻り、これが学生の支持を得ることになった。
すでに「伝説」化していたガスリーもこの時点で再注目されるようになった。
彼らの代表的な歌は、白人に殺された黒人を歌った「トム・ドゥーリー」、サッコ・ヴァンゼッティ事件を扱った「サッコとヴァンゼッティのバラード」などだが、
この曲名を見ても学生が彼らのどんな部分を評価をしていたかがわかる。
彼らの影響を受けた学生達は次々とフォークグループを結成し、古い歌や自作の歌を歌い始めた。
これが「モダンフォーク」である。
「サッコ・ヴァンゼッティ事件」(アメリカ史上最悪のえん罪事件。イタリア移民で無政府主義者のニコラ・サッコとバルトロメオ・ヴァンゼッティという人物が、
強盗殺人事件の犯人に仕立て上げられ、死刑に処されてしまうという事件。
彼らをえん罪から救うために家族や友人は弁護士を雇って裁判を戦うが、検察側が仕組んだ偽証や、元々ある移民差別、思想差別の風潮により、
証拠不十分のまま有罪が確定。1921年に死刑が宣告されてしまう。
このことが自由主義者達の再審請願運動を呼び起こし、アメリカのみならずロンドン、パリ、ローマなどヨーロッパ各都市での請願運動が始まった)
1959年には「キングストントリオ」の「トム・ドゥーリー」がなどが大ヒット。
同年には第一回の「ニューポート・フォークフェスティバル」が行われるなど、モダンフォークブームは盛り上がった。1960年代になってもこのブームは続く。
時はまさに政治の季節であり、キューバ危機、ベトナム介入、黒人公民権運動などに対応する学生運動が盛んになり、
フォークソングはそんな学生の為の意見表明の格好のメディアとなった。
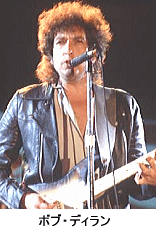
1959年のフォークフェスティバルに登場しスターとなったジョーン・バエズ(Joan Baez)が歌った「ドナドナ」は、
徴兵されベトナムに連れていかれる若い兵士を屠殺場に連れていかれる子牛にたとえて歌ってものであった。
1963年にデビューしたボブ・ディラン(Bob Dylan)の「風に吹かれて」「戦争の親玉」「激しい雨が」なども明らかに「プロテストソング」であった。
このころ、1950年代は「ビートニク」で詩とジャズに湧いたグリニッチビレッジにはフォークシンガー達が集結し多くのカフェがその発表の場となっていた。
また各大学でもフォーク活動は盛んになり、当時アメリカはまさに「フォークの時代」であった。
2)フォークの日本への移植〜第一回目〜
モダンフォークは1960年には既に日本に紹介されていた。担い手はもちろん大学生である。
戦後大学生は、戦勝国アメリカの音楽に夢中になった。
学生にとってアメリカ音楽は「モダン」の最先端として認識されており、戦後極東放送を通じて聞くことが出来た「カントリー&ウエスタン」「ジャズ」「ハワイアン」が
こうしたものとして人気を得、大学のサークル活動としても広く行われていた。
1960年のフォークブームはこのような「アメリカへのあこがれ」の一環として起こったのである。
キングストントリオやジョーン・バエズ、ピーター・ポール&マリーらも続々来日、国内では小室等が日本初のフォークグループを結成し、マイク真木が学生スターになるなど
「知的でファッショナブルな歌」としてフォークブームは盛り上がった。
しかし高度成長真っ最中であり、オリンピックにわく60年代中盤には、アメリカで主流になっていたディランらのプロテストソング系は受け入れられず、やがてブームは下火になる。
3)フォークの日本への移植〜第二回目〜「全共闘世代文化」としてのフォーク
しかし1960年代後半、フォークは意外なところで息を吹き返した。
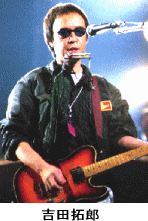
共産党系の「うたごえ運動」は関西では特に根強く、60年安保・原水禁運動・三井三池・ベトナム反戦などの活動への動員を「歌」によって行ってきたが、
その傍流から「プロテストフォーク」が生まれてきたのである。
岡林信康の「くそ食らえ節」「山谷ブルース」、高田渡の「自衛隊に入ろう」、高石友也の「籠の鳥ブルース」などが67年から68年にかけて登場し東京にもあっという間に伝搬した。
これらはもちろんディランらを参照して作られたものであるが、岡林信康の詩は今までに無い、借り物でない日常的な言葉で書かれており、1970年安保前夜であり、
ベトナムが泥沼化し、公害も問題化し、成田の土地の強制収用へ向けての動きが活発化したこのころ、政治的意識を先鋭化させていた学生達の共感を呼んだのだった。
全国的に行われた学園闘争や各種の政治活動にのめりこみ、デモや集会が日常であった全共闘世代の学生は岡林らに衝撃を受け、彼らを経由してディランらを知り、
自らギターを手に取ってプロテストソングを歌う者が続出した。
1960年代初めには知的ファッションとして流行したフォークは、この時期には「メッセージ性」故に学生達に受け入れられたのである。
1969年には新宿西口広場で安保やベトナムに反対するプロテストソング集会が開かれ、岡林らの歌が歌われ、毎回数千人を動員したが警察に規制され、
小競り合いから逮捕者を出すようになり、やがて中止させられる。
実際の活動家である新谷のり子が、ベトナム戦争に抗議して焼身自殺したパリの学生のことを歌った「フランシーヌの場合」を唄い大ヒットする、などということもあった。
4)全共闘の挫折と「日本のフォーク」の時代
しかし1970年、安保が自動延長になると、学生運動はそれまでの高揚感を失い、一挙に沈静化した。

行き場を無くした活動家はテロ的行為にはしり、あるいは内ゲバに終始するなど、学生運動はもはや一般の政治的学生を引きつけるものでは無くなってしまった。
岡林やディランを知って、かつてはプロテストソングを唄った学生も、もうプロテストソングは唄えなかったのである。
1969年に結成された「クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング(CSN&Y)」は「ウッドストック」を象徴的するグループであったが、ディランに代わって彼らに人気が集中した。
モダンなハーモニーやオープンチューニングによる独特の和声、透明感のある声が人気を博し、プロテストソングを唄っていた連中の多くは彼らをコピーした。
「かぐや姫」「アルフィー」「ガロ」などのグループはこのような流れから誕生した。
また、この年に吉田拓郎が登場したのは象徴的なできごとである。
吉田には既にディラン的・政治的なものはなかった。替わりにあるものはこの世代の戦後的なものから切れた「新しさ」であった。
1972年の「結婚しようよ」は、長髪の若者の確かに旧世代と異なる価値観が語られているが、既に70年の最初のアルバムのタイトル「新しい船を動かせるのは古い水夫じゃないだろう」
には「新しいということ」の絶対的な価値が訴求されている。この姿勢は全共闘世代を勇気づけた。
学生運動や革命には挫折した駄目な彼らだが、自分たちがただ単に「新しいこと」で、それだけで価値がある存在なのだ、ということになったからである。
全共闘世代の「根拠のない自己肯定」はここで確立した。
彼らはやがて企業戦士となり、金を稼ぎ、モノを買いまくり、「友達夫婦」「ニューファミリー」といった「新しい」価値観を追及し、バブルをあおり、
ロクでもない子供を育てて今でも自分たちが時代の最先端にいると思っているのである。
彼らの政治的挫折は、拓郎的な夜郎自大精神によって大いに癒された。その一方でこの時代の歌は奇妙な喪失感に満ちてもいる。
「風」(1970年・はしだのりひこ)、「花嫁」(1971年・はしだのりひこ)、「あのすばらしい愛をもう一度」(1973年・北山修&加藤和彦)、岬めぐり(1973年・山本コータロー)、
「学生街の喫茶店」(1973年・ガロ)「神田川」(1973年・かぐや姫)などはすべて「昔あった良い時代を哀惜する」という感情に裏打ちされた歌である。
これは敢えて言うまでもなく前年の「浅間山荘事件」を含む「連合赤軍事件」を受けたものだからだ。
彼ら全共闘世代の「革命感情」は70年にすでに挫折していたが、この「連赤事件」は、革命の不能性・革命の時代の終焉をくっきりと彼らに確認させたのだった。
「学生街の喫茶店」においては、昔<ふたりでよく聞いていたボブ・ディラン>は今<あの時の歌(ボブ・ディラン)は聞こえない/人の姿も変わったよ/時は流れた)と唄われ、
プロテストのディランの時代=革命の時代の終焉が記されている。
かつての革命感情の喪失が明らかになったのが1973年であり、これらの歌はこの喪失感情から立ち上がって来たのである。
5)「転向=挫折」隠しから生まれた「叙情派フォーク」「四畳半フォーク」
「かぐや姫」らの歌は「叙情派フォーク」と呼ばれ、このような傾向の曲は「フォーク」の主流となった。
今でも「懐メロ」的テレビ番組で唄われることが多いのはこの手の歌であるし、「日本のフォーク」といえばこのような曲のイメージを思い浮かべる人も多い。
しかしなぜ「叙情派」が主流になったのか。
それは、「革命の挫折」に対しての喪失感が、この時代の「叙情派」の詩の磁場を形成していたことがポイントである。この時代の歌の歌詞を見ると、ある不思議な特徴がある。
それは「今、昔を哀惜している、という感情」と、「今と昔の間に<決定的な何か>が起こっているのだが、それが何かは絶対に明かされない」という2点である。
例えば「学生街」では<ボブ・ディランを聞いた時代>を<あの時の歌が聞こえない現在>から懐かしむ曲だが、今と昔を隔てている断層が何なのかは決して言及されない。
なぜ時代が変わったのか。時代のために自分は変わったのかどうか。こうしたことには一切触れない。
また「神田川」でも同じ事態が起こっている。
<なにもこわくなかった>昔と、今それを懐かしむ自分の存在はわかるのだが、「昔と今を隔てているのは何か」はここでも明らかにされないし、「今」の自分がどんな存在なのかも問われない。
「岬めぐり」でも<あなたが昔教えてくれた>岬を今訪ねるわけだが、何があなたと私を切断したのか、また、昔と今が何によって切断されているかは語られない。
「昔と今」の切断。その原因の隠ぺい。これらの歌はこうした観点からは全く同じ構造を持っているのである。
そして隠されたものとは「挫折=転向」なのである。
このことを証明するためには、「22才の別れ」(1975年・伊勢正三・元かぐや姫)を見てみるのが最適だ。
表面的には、「あいまいな関係を続ける過去の男を断ち切って、別の男との結婚を決めてしまった女の心情」を唄っているように見せかけているが、実はこれは「転向」の歌である。
「あなた」を「革命」に、「嫁いでいく」「目の前のしあわせ」を「就職」に置き換えてみるとよくわかるのだ。
<永すぎた春>とは、「政治に肩入れしても、革命が実現しなかった・結果が出なかった年月」を意味し「22才」とは大学卒業の年齢だ。
卒業と同時に就職し、運動から離れることへの罪悪感がここに表出されている。
これが本当に男女のことを唄った詩なら、「卒業=22才」ということが絡んでくる必然性はないのである。
実は「叙情派フォーク」といわれる作品のほとんど全てはこのような構造をとっている。
「22才の別れ」では、「革命」と「自分」との関係を、不条理な部分が忍び込むのが当然の男女関係に置換し、「革命」を捨て「就職」に走る「自分」を、
「目先の幸せに目がくらむ、女のバカさ、不可解さ」という通念的イメージに喩えることで、自分が「革命」を捨てたことを「女のバカさ」によって納得する、
という案外手の込んだように見えて最悪なレトリックが行われている。
「神田川」でも、貧しさの中の革命感情を<若かった故の怖いもの知らず>として「男女関係」や「若さ」という常套的な概念に置き換えて納得させている。
「岬めぐり」ではやはり失った「革命感情」を「昔の女」に喩えたうえで<くだける波のあの激しさで/あなたをもっと愛したかった>と唄う。
そして、別れた今は<僕はどうして活きていこう/悲しみ深く胸に沈めたら/この旅終えて町に帰ろう>と、革命の喪失感と社会(就職)への復帰を誓うわけである。
「学生街の喫茶店」でも同様に男女関係を比喩として導入するが、相手と別れた理由は問われずただ「時は流れた」という「時間の経過による人の心の変化」というありきたりな結論が導かれる。
要するに「叙情派フォーク」といわれる大きな潮流は「転向」「挫折」を隠ぺいしながらも、「その失意だけは語りたい」という欲望から生まれた陰喩空間を指すのである。
「男と女」「昔と今」という対立軸から成立する、手垢にまみれた陰喩の連鎖。
しかしその中心である「挫折」は決して語られないという、不誠実さに満ちた欺瞞的な詩空間なのだ。
しかし革命の挫折・喪失感を「男女関係」「今から昔を懐かしむ」という形に置き換えていくこの方法論は、専門的な詩人でなくてもそれなりの詩的磁場を形づくることが容易であり、
結果同じような趣向の曲が沢山誕生することとなったわけである。
それにしても、なぜこんなタイプの隠喩法が採用されたのか。「革命の挫折=転向」が隠れた主題なのに、なぜそれが決して触れられないのか。
それは全共闘世代の世代的な特性に求めることができる。
吉田拓郎的夜郎自大的自己肯定を手にした彼らは「転向」を決して認めようとしなかったということである。
普通、ある社会思想・政治思想に基づいて行動を行ったものが「挫折」するとき、その思想と自分の関係の徹底的な洗い直しや批判がそのその人の中で行われる。
その思想は果たして正しかったのか、その思想の意味は何か、その思想の可能性と限界はどこにあったか、自分はどのようにその思想を理解していたか、
自分がかわったとすればそれはなぜか、変節したことは正しいのか誤ったことなのかなどなどと考える。
そうでなければ先に進めないし、コミットしていた期間が無意味なものになってしまう。経験から何らかの教訓を引きだし先に進もうとするなら、そうするしかないのである。
昔の自分はそうすることで今に活かすことができるのである。しかし彼らはそれを行わず、そのことを歌わなかった。
自分の過去を自己批判せず、不問に付し、ただ感傷にくるんで「思い出」にしてしまったのである。
全共闘世代は今に至るまで、あの時代の自分の思想と、自分がその思想を裏切る生活をしていることを論理的に自己批判することはなく、
一貫した「自己」を持てないでいるのだが、この時代の彼らの産物「フォーク」に、すでにその姿勢の全てが現われているのである。
さてこのような自己欺瞞に基づく不誠実な表現=日本のフォークはロクな果実を生み出すはずがなく、やがて行き詰まる。
そして彼らに引導を渡したのは彼らの後発世代・非全共闘世代の荒井由実であった。
彼らの不誠実さに当然ながら批判的な彼女がやったことはアクロバチックで見事なものだった。
彼らの「昔を懐かしむ」詩のスタイルをそのまま利用し、それを逆手にとって 「いちご白書をもう一度」という「叙情派のパロディ曲」を書くことによって全共闘を批判したのである。
6)「全共闘世代表現」としてのフォークの破産
「いちご白書」というのは映画の題名である。ノンポリの大学ボート部員・サイモンがスト中のキャンパスで活動家リンダに一目ぼれする。
そしてリンダに気に入られたい一心から政治活動に深入りしていく、という学園闘争モノの映画であった。
ユーミン(松任谷由美)は、叙情派と完全に同じ形式「男女」「今/昔の時間軸」を使って「叙情派フォーク」のパロディー詩を書いたのである。
そっくりだけれど、全共闘世代が絶対に触れず、タブーにしていたその叙情フォークの核心をあえて書くという点での決定的な差異。
その核心とは<僕は無精ヒゲと髪を伸ばして/学生集会へも時々出かけた/ 就職が決まって髪を切ったとき/もう若くないさと君に言いわけしたね>に見られるとおり、
「運動から就職へという転向」である。
ご丁寧にも、「運動」を自己批判なしに「思い出」にしてしまうという全共闘特有のグロテスクさも<二人だけのメモリーいつかもう一度>と歌って茶化しているのだ。
「学生街」「岬」「神田川」「22才」などでは絶対に語られず空白だった秘密の部分がここでついに暴露されてしまったのである。
ユーミンらしからぬ筆致をあえて採用して彼女が暴露したのは、決して語られない「転向=挫折」の周囲に陰喩を積み重ねることで成立していた「叙情派フォーク」の詩空間の欺瞞性であり、
それはこのとき誰の目にも明らかになったのである。
ユーミンはさらに全共闘のフォークを「四畳半フォーク」と名付けて攻撃し、最悪に鈍感な同世代ファンや後発世代のフォロワーたちさえも「全共闘表現」としてのフォークに見切りをつけることになった。
この1975年を期に、ギターはケースやら押し入れやらにしまい込まれることになる。「フォーク」は、全共闘より下の世代では、「恥」と同義語になったのである。
「フォーク」という言葉はほとんどタブーになり、ユーミンに先導される「ニューミュージック」といわれるスタイルが全盛となっていく。
「かぐや姫」「ガロ」などのグループも次々と解散していった。
7)終焉以後
公平を期すため、安易な叙情派に与しないシンガー達がいたことも記しておく。遠藤賢司は「転向」を巡る事態に自覚的だった。
「カレーライス」ではアパートで彼女がカレーを作り猫が甘えてくる幸福な、しかし閉塞した日常が語られるが、野菜を切る音を聴きながらふとみたテレビには臨時ニュースが映る。
<おなかを切った人がいるんだって/いたかったろうなあ>。
おなかを切った人というのはもちろん三島由紀夫のことだ。しかしこの詩の主人公はこの事件を政治的文脈では考えようとしない。
<いたかったろうなあ>。革命に敗退して引きこもった人間の、あえて政治を拒否する、強い挫折感や泥のようなニヒリズムを客観的に表現している。
転向の意味を執拗に考える姿勢がここにあるのである。
他にも加川良や井上陽水、小椋佳、中山ラビなども「転向」を巡る潮流に流されることなく自分の世界を持った人だった。
さだまさし(グレープ)なども、善し悪しはともかく文藝調と言える独自の世界を構築しておりこうした流れとは「無縁」であった。
要するに欺瞞的でない、全共闘的でない、「正しい詩人の資質」を持った人は特定の支持を集めることができたのである。
しかし1970年代後半の音楽状況は、しばらく「フォーク的なもの」の延命をはかることになった。
1970年までにロックを創造したカリスマ達、ドアーズ・ジャニス・ジミヘン・クリームなどはすでに消滅していた。
当時のシーンには、サザンロック(オールマンブラザーズなど)シアトリカルロック(クイーンなど)・グラム(デヴィッドボウイなど)・プログレッシブロック(イエスなど)・
ハードロック(レッドツエッペリンなど)・シンガーソングライター(エルトンジョンなど)・ポップス(カーペンターズなど)など極めて多彩な音楽が登場していた。
洋楽は多様化、趣味化してしまったのである。
歌謡曲シーンでは「ピンクレディ」「キャンディーズ」「沢田研二」らのアイドル系歌手や「森進一」や「八代亜紀」などの演歌系歌手が全盛を極めており、
こうした状況に付いていけないが、しかし「個人の表現のようなもの」にこだわりたい音楽ファンは、敷居の低い日本のフォークにまだ固執した。
1975年以降も「フォーク的」な歌手のニーズは限定的に存在したのである。
それに応えるのがアリスや松山千春や長淵剛、アルフィーであった。
この人たちの特徴は、その詩の内容の空疎さ、抽象性と拓郎譲りの自己肯定、批判意識のない説教臭さであった。
しかし1975年以降もこれらの人たちは 「深夜放送」の「パーソナリティ」を勤めることに支えられて人気を持続することができた。
長淵らの表現の誕生は、全共闘シンガーたちが「転向=挫折」を自分のものとして受け止めなかったために必然的に起こった事態である。
後発世代の彼らは形式やかっこいいところ、えらそうなところだけ全共闘シンガーをまねたのだ。しかしこれはもうジャンルにとっての末期症状であった。
サウンドももうアメリカのフォーク起源のものとは何の関係もなくなり、「ニューミュージック」と呼ばれるものとの区別はなくなった。
全共闘の世代文化であった「フォーク」は全共闘の世代的特性によって自壊し、またそれをまねしたフォロワーたちの表現も自壊したのである。
1960年後半からの「日本のフォークの時代」は、1975年、ユーミンによる「四畳半フォーク批判」の時点ですでに終わっていたと考えるべきである。